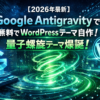【タイの田舎の小さな家から】光と影の詩:ワット・アルンと三島由紀夫の美学

光と影の詩:ワット・アルンと三島由紀夫の美学

光と影の詩:ワット・アルンと三島由紀夫の美学
バンコクのチャオプラヤ川に佇む ワット・アルン(暁の寺) は、私の心を最も強く惹きつける寺院です。朝日に染まる白亜のプラーンは、まるで時空を超え、静謐な光の海に浮かぶよう。塔の細やかな装飾は、陶器や貝殻が光を反射し、川面に無数の煌めきを映すたび、息を呑む美しさを見せます。
この景色に立つと、私の頭に浮かぶのは、愛読書である三島由紀夫の『豊饒の海』の世界です。三島が描き出したのは、時間の流れの中で美と死生観が交錯する瞬間。ワット・アルンの塔を見上げると、川に映る光と影のコントラストが、まるで小説の頁から飛び出してきたかのように、精神の深奥と呼応します。
ワット・アルンの歴史と象徴性
ワット・アルンの歴史は18世紀末に遡ります。トンブリー王朝の時代から整備され、ラーマ2世・3世の時代に現在の荘厳な姿に完成しました。高さ約70メートルのプラーンは、川の流れと都市の喧騒を見下ろし、訪れる者に静謐と祈りの時間を提供します。塔を登るごとに広がる視界は、まるで人間の内面が広がるかのようで、三島が愛した「形と精神の一致」を体感させてくれます。
三島文学との響き
三島由紀夫の文学では、儀式や伝統、そして美への追求が登場人物の精神世界と密接に結びつきます。ワット・アルンもまた、装飾や光の移ろいを通して、形と精神、現実と象徴が交差する場となります。塔の白い壁に差し込む朝日の光、川面に映る影の揺らぎ──その一瞬一瞬が、三島の筆致で描かれる美の概念と重なるのです。

個人的な感慨
何度訪れても、ワット・アルンは飽きることなく私を魅了します。塔の頂から見下ろすチャオプラヤ川の輝きは、『豊饒の海』の頁に描かれる人間存在の儚さと美の絶対性を呼び起こします。ここに立つと、文学と現実が交錯し、異国の寺院でありながら、心は深い郷愁と陶酔に包まれるのです。ワット・アルンは、私にとって単なる建造物ではなく、三島文学と響き合う魂の舞台なのです。

個人的な感慨
何度訪れても、ワット・アルンは飽きることなく私を魅了します。塔の頂から見下ろすチャオプラヤ川の輝きは、『豊饒の海』の頁に描かれる人間存在の儚さと美の絶対性を呼び起こします。ここに立つと、文学と現実が交錯し、異国の寺院でありながら、心は深い郷愁と陶酔に包まれるのです。ワット・アルンは、私にとって単なる建造物ではなく、三島文学と響き合う魂の舞台なのです。

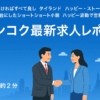





|-タイから応募可能な世界の小説コンテストまとめ-(日本語・英語-公募完全統合版)-‹-Imagine-Happy-AI-L-300x201.png)